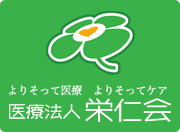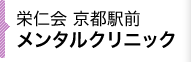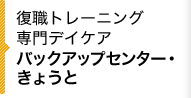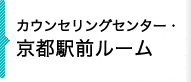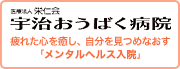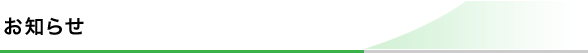京都市 下京区 心療内科 精神科 メンタルクリニック カウンセリング 復職トレーニング専門デイケア
- ホーム >
- お知らせ
BUCきょうとのブログ
2020年12月17日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第106回「私流 禁酒・禁煙法」
-
私は、BUCに通所を始めた頃、毎日発泡酒を1本と缶チューハイを2~3本飲むのが最大の楽しみでした。また、タバコも20年以上、毎日10~15本を吸っていました。それがストレス解消法だと思っていたからです。
しかし、通所を始めてまもなく、スタッフの方から飲酒をやめるように指摘されました。精神疾患で薬を服用している間は飲酒は厳禁とされていましたので、「少しは減らすようにするか。」と軽く考えていました。しかし、その後も厳しく指導をされ、「本当にマズい状況だな」と思い始めました。
大好きなお酒。やめたくない気持ちが強かったのですが、禁酒に向けて動くことにしました。
そこで、私が取った方法は、①1か月後に完全禁酒する日を設定、②それまでは、「マズい」と思いながらお酒を飲む、③炭酸水を飲み、「お酒と変わらない」と思い込む、というものでした。
これが功を奏し、最初に設定した禁酒日以降は一切アルコールを摂取することなく、現在130日継続しています。
そして、禁酒ができたことで自信がつき、禁煙にも取り組むことにしました。禁煙も同様の方法で取り組み、現在85日継続しています。
「我慢をしてやめる」というのはとても厳しいこと。お酒やタバコは依存性が高いので、本当に自分が摂取したいと思って摂取しているのか見直したら、案外摂取したいなんて思っていなくて、簡単にやめられるのかもしれません。
ペンネーム:Y.T
2020年12月 3日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第105回「お薦めのパン屋さん」「体の中から温まろう(約600kcal~あなた次第)」
-
今回は2本お届けします。どちらも美味しい話ですよ!
<お薦めのパン屋さん>
京都の、有名なパン屋さんで思い出すのは、志津屋さんです。京都駅にも2店舗あり、BUCの帰りについつい寄ってパンを買ってから帰ることもあります。売れ筋のカルネとビーフカツサンドが、特に美味しいですね。高校の文化祭で、学校から支給してもらってからのファンです。カフェが併設されているお店もありますね。
もう一つは、宇治の黄檗にあるたまき亭です。美味しさが有名になって、色々なメディアに取り上げられています。何回か買いに行ったことがありますが、いつも長蛇の列を並んでから買う感じですね。お店以外にも近くに駐車場が五つあります。毎週月、火、水曜日が定休日です。もし近くに行かれたら、寄ってみるのもいいかもです。
ペンネーム:ハンゾウ
<体の中から温まろう(約600kcal~あなた次第)>
今回のブログのお題例にあった、炭水化物もりもりの鍋。それを見て思い出したのは、体温を上げたいときに食べる鍋焼きうどんだった。
材料はスーパーで冷凍うどん、うどん出汁、ねぎ、えび天(できれば天かす追加で)、玉子を確保する。かさを増したいなら、麩を入れるのもいい。好みで鶏肉、しいたけ、ほうれん草なども入れるとタンパク質も食物繊維も摂れて、よりおいしい。(自分では面倒で入れないが勧めていくスタイル)
そして、忘れてはいけないのが、ご飯である。できれば炊き立てでない冷ご飯。
なお、桃〇の濃縮2倍つゆを用意しておくと重宝する。〇屋の濃縮2倍つゆはいい。テーブル〇―クの冷凍蕎麦をレンチンして、これに刻みネギ、海苔、チューブわさびを用意するだけで、けっこうおいしいざる蕎麦が食べられる。おろし生姜とおろしにんにくのチューブも便利。
脱線したが、本題は鍋焼きうどんである。
小さい土鍋に冷凍うどんとうどん出汁を入れて中火でしばらく煮る。(野菜を入れるならうどんを入れる前に別口で軽く茹でておいて、一緒に入れる)うどんがやわらかくなったら、えび天を入れて玉子を落とし、ふたをする。玉子が好みの硬さになるのを待って、完成。
えび天をざくざく崩して、さあどうぞ。温まっても歯ごたえの残る冷凍うどんは、よく噛んで。玉子と天ぷらの衣がうどんに絡み、お腹から体が温まる。勢いに乗って出汁も全部飲んでしまいそうになるが、ここはちょいと我慢して、具とうどんだけ、たいらげる。
第二ラウンド、そこに冷ご飯を投入。出汁が少なくなっていたら、桃〇のつゆを入れて調整。天かすマシマシ玉追加もアリ。味を変えるのにショウガとニンニクをちょっと入れたりして刻みねぎをまた入れて少し火にかけ直せば、ご飯に天かすの油の甘さ残る出汁がたっぷり染み込んだおじやができあがる。
炭水化物を堪能できて体もポカポカ、鍋焼きうどん。翌日運動すれば某スタッフさんに怒られない!……といいな。
ペンネーム:CH
2020年11月20日 (金)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第104回『EQ』との出会い
-
とうとうブログを書く機会が回ってきた編集員A.Nです。いざ、ブログ記事に何を書こうか正直迷っておりました。迷っている状況の中、私の中で課題となっている感情をうまくコントロールできない問題があり、課題図書でも感情に関連する本を読んでみたいという気持ちが湧き上がり、感情についての本を手に取って読んでみることにしました。その本の中で、『EQ』という言葉が出てきて「心の知能指数」ということを知りました。そして、IQ(Inteligence Quotient:知能指数)では測れない能力を示すものと紹介されていました。IQでは測れない能力で自分にとってはとても大事なことなのかもしれないと感じ、迷わず『EQ』に関わる本を購入して詳しく読んでみようと思い、また、その話を少し掻い摘んでブログに載せてみようと思った次第です。
さて、『EQ』ということば自体、馴染みのない言葉で私自身も知りませんでした。『心の知能指数(Emotional Inteligence)』すなわち『EQ(Emotional Intelligence Quotient)』は、脳の中の感情と理性のコミュニケーションから生み出されます。これだけだと、何のことを言っているのかわかりませんが、もう少し噛み砕くと『自分自身と他者の心の動きに気づき、それを理解する能力』のようです。また、『その気づきを使って自分の行動や人間関係を上手にマネジメントする能力』でもあるようです。EQはどんな人の中にもありますが、目に見えにくいものです。EQの力が、行動をコントロールできるか、複雑な社会の中をうまく進めるか、賢い判断によって前向きな結果を出せるかを左右します。
ルーティン・ワークを行う際には、側頭葉と頭頂葉しか使いませんが、新しい状況に適応するとか、これまでにないものを生み出していくときには前頭葉を使うと考えられています。IQは脳の側頭葉や頭頂葉の機能を測るものですが、EQは脳の前頭葉の働きを表すものです。逆説的に考えると、前頭葉の働きが良い人はEQの働きも良いことになります。ただ、前頭葉は40代を過ぎると物理的にも萎縮し始めます。年齢を重ねていけば、経験も増えるのでEQが向上するように思われがちですが、この物理的な萎縮と教育・知識・経験による刺激が少なければ萎縮が勝りEQの向上を妨げることにつながるのです。私も40代に足を踏み入れようとしておりますが、教育や知識、経験の刺激を萎縮より増していけば、年齢を重ねてもプラスの方を上回らせることは難しくないと考えています。
他方、IQは20代をピークに70代になってもあまり低下しません。なので、理解力はあまり落ちないということになります。となると、知能の老化を気にするよりは感情の老化を気にする方が良いのかもしれません。
いろいろと、EQのことについて記載しましたが、まだまだ書き足りないことが多く、もっと伝えたいという気持ちでいっぱいです。ただ、記事にも制限があるので、下記に参考文献を載せました。これを読んで下さった皆様のご興味の一助となればと思います。
参考文献:「感情に振り回されない人」の脳の使い方(著者:和田秀樹)
「EQ2.0」(著者:トラヴィス・ブラッドベリー、ジーン・グリーブス)
ペンネーム:A.N
2020年11月 5日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第103回『女性メンバー座談会 ~BUCで良かったこと~』(後編)
-
情報発信係のY.Tです。今回は、「女性メンバー座談会 ~BUCで良かったこと~」(後編)をお届けいたします。
(情報発信係Y.T)
普段は女性メンバー同士でお話はされるのですか?
(もりもりプリンさん)
以前は女性メンバーが4,5人集まってお昼を食べてましたけど、コロナの影響で、集まって食べることはなくなりましたね。普段ちょこちょこと話をしている感じです。
(焼き栗さん)
コロナの関係で集まれないしね。食事の時が一番話しやすいのに、それができなくなったのが残念。
(情報発信係Y.T)
BUCに通所を始めた時に、不安に思ったことはありますか?
(もりもりプリンさん)
最初は、周りの人の体調がわからなかったので、どう話しかけて良いかわからず、1ヶ月半くらい様子見していました。
(焼き栗さん)
自分の体調が悪かったり、コロナのこともあったりで、つい「話しかけるのはやめとこうか」となってしまう。そんな中で、私に話しかけてくれた人には本当に感謝しています。
(もりもりプリンさん)
今はステージが上がり、自分のことで精一杯で他の人に声をかけられていないですね。先輩は色々としてくれてありがたかったので、自分も頑張ろうと思います。
(情報発信係Y.T)
BUCで話しやすいプログラムはありますか?
(わらびもちさん)
クラフトが一番話しやすいな。
(もりもりプリンさん)
しんどかったら話さなくていいですしね。作業がメインですしね。
(焼き栗さん)
クラフトで最初の会話が始まる感じだね。そこで名前も覚えた。
(わらびもちさん)
基本はステージ1が終わったら、参加ができないよね。
(もりもりプリンさん)
私は人数の関係で中退になりました(泣)。クラフト楽しかったなぁ。
(わらびもちさん)
個々の作業ではあるけど、集まってやるのがいいよね。
(もりもりプリンさん)
休職してから話をする人って、家族か友人もしくは病院の人だけでした。クラフトで初対面の人と雑談したとき、社会に戻る一歩のような気がしました。「人と話すのってこんなに楽しいんだ」って思いました。
(焼き栗さん)
久しぶりにドラマの話とかした。クラフトも慣れてくると、テーマなしで話せるようになるよね。
(情報発信係Y.T)
今はどのようにコミュニケーションを取っているのですか?
(もりもりプリンさん)
「振り返りミーティング」の後に、続きで雑談したりとかかなぁ。
(焼き栗さん)
「週末どのように過ごしたか」という話の続きとかで。「こんな楽しみ方もあるんだ」と発見があるのが嬉しい。
(もりもりプリンさん)
自分の生活を人前で話をする機会もなかったですよね(笑)。
(焼き栗さん)
どこまで話をしようか葛藤があったり(笑)。
(もりもりプリンさん)
「振り返りミーティング」が終わった後に、ホワイトボードを見ながら他の人と話すのも良いコミュニケーションになりますよね。
(わらびもちさん)
自分の班以外のホワイトボードを見るのも面白いよね。
(情報発信係Y.T)
「こんなプログラムがあったらいいな」というのはありますか?
(焼き栗さん)
以前は「振り返りミーティング」で女性だけが集まって話す機会があったらしいよ。最近は女性の人数が少なくてできてないけど、だんだん多くなってきたので、それができたら嬉しいな。2ヶ月に1度くらいは。
(もりもりプリンさん)
面白そう。1回やってみたいな。
(編集後記)
座談会形式でブログに載せるというのは、今回が初めての取り組みでしたが、女性メンバーの率直な声を聴くことができ、とても有意義な座談会であったと思います。今後もこのような取り組みを通じて、メンバーが楽しく通所できるような情報を発信していきたいと思います。
ペンネーム:Y.T
2020年10月22日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第102回『女性メンバー座談会 ~BUCで良かったこと~』(前編)
-
情報発信係のY.Tです。先日、BUCに通所されている女性メンバー3名に集まっていただき、「BUCで良かったこと」をテーマに座談会を開催しました。
今回と次回のブログでは、そこで出された女性メンバーの方の声を前編と後編に分けて、御紹介させていただきます。
(もりもりプリンさん)
BUCで良かったことは、人とのふれあいです。ここのプログラムでは、自分の発言や振る舞いに対してフィードバックがもらえます。また、今までの自分のコミュニティにいなかったタイプの方と趣味の話とかができるのが楽しいです。職場ではどうしても似たような人ばかりでしたね。
(わらびもちさん)
BUCの女性メンバーは少ないね。私は5月の連休明けから通所してるけど、最初は、女性メンバーが集まっている中になかなか入って行けなかったなぁ。みんなとお話ができるようになったのは、もりもりプリンちゃんが声をかけてくれてから。BUCではクラフトがあるけど、作業をしながら気軽に話せるのがいいよね。今は、私も新しく入ってきた人が少しでも気が楽になるように話しかけてあげたいなぁ。
(焼き栗さん)
BUCでやっていること全てに意味があると思う。特に、「振り返りミーティング」では、「苦手な人との話し方」などをテーマに、普段の職場では絶対に話題にしないことを話すから、とても新鮮に感じたよ。ただし、やっぱり女性が少ないね。あまり男女の比率は気にしていないけど。
(もりもりプリンさん)
私は2年前にも通所していたことがありますが、その時には女性はもっと少なかったですよ。学校とか職場では女性が多い環境だったから、その時はなかなか慣れなかったなぁ。今では私も大分回復してきたし、性別や年齢の垣根も超えて、皆さんと楽しくお話ができるようになりました。
BUCに通所している女性メンバーは、みんな「会社を辞める」という選択をせずに、職場への復帰を目指しています。そこに親近感や連帯感を感じています。結婚していたり、子供がいたりと立場の違いはあるけれど、目指すところがみんな同じだから、一緒に頑張れるんですよね。
(情報発信係Y.T)
BUCで楽しかったことはありましたか?
(わらびもちさん)
納涼会が楽しかったよね。
(もりもりプリンさん)
実行委員の方のおかげですごく楽しかった。盆踊りの練習もよかったですね。
(焼き栗さん)
他にも楽しいイベントってあるの?
(もりもりプリンさん)
忘年会か新年会もあるらしいですよ。
(わらびもちさん)
OB交流会もまたあるよね。
(もりもりプリンさん)
2ヶ月に1度くらいは何かしらのイベントがありますね。楽しいイベントは忘年会または新年会、そして納涼会。「やりたくない」という人は一人もいなかったです。
(わらびもちさん)
だんだんゲームでも真剣になってきたね(笑)。
(もりもりプリンさん)
白熱してきますよねー。
(焼き栗さん)
職場では、こんなイベントはあまりなかったなぁ。
(もりもりプリンさん)
余暇も大事ですよね。復職に向けてリハビリをしているからといって、真面目なことばかりでもよくないと思います。楽しい時間を持つことも大事ですよね。
続く・・・(次回は11月5日頃に更新予定です。)
ペンネーム:Y.T
2020年10月 8日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第101回 マインドフルネスとは?
-
このマインドフルネスという言葉、このメンバーブログでもよく見かけますし、「気になってはいる」、「でもどんなものなのか分かりづらい」、「ちょっと抵抗がある」という方は少なくないのではないでしょうか。私もそのうちの一人でした。仕事で疲れ切っていた私は、リラックス方法としてこのマインドフルネスという言葉にたどり着き、「Google社などでも取り入れられているなら効果があるに違いない」と独学で試してみていましたが、あまり効果が得られませんでした。
結論から先に言ってしまいますと、今はマインドフルネスをうまく活用し、メンタルを改善したり、リラックスしたり、さらには集中力を得ることまでできるようになりました。ここまで書いていて自分でも胡散臭さを感じてしまいましたが、確かに効果はありました。いつも成功するという訳ではありませんが、以前よりは確実に良い方向に向かっていると感じます。
今回は私なりに、マインドフルネスについてのプレゼンをしてみたいと思います。人に教えられるほどのものではありませんが、この記事で興味を持って頂いたり、誤解などが解けて「やってみようかな」と思って頂けたら幸いです。
まずはマインドフルネスについて私の考えを挙げておきたいと思います。
①マインドフルネスはスピリチュアルなものではなく、脳のトレーニングに近いものである
②マインドフルネスは辛い修行のようなものではなく、ノーリスクハイリターンな簡単な取り組みで
ある
③マインドフルネスは休憩の手段ではなく、休憩の質を高める手段である
マインドフルネスは、瞑想と切っても切れない関係にあります。瞑想というと「無の境地への到達」や「宇宙の真理(?)」など、どうしても宗教観のある怪しげなイメージを持っていた私ですが、実際のマインドフルネスでは一切そういったことは考えません。マインドフルネス中に意識しているのは、次のことだけです。
「自分は今、何を感じ、考えているのだろう」
日頃の生活の中、自分の身体・思考が自動的に動いてるように感じることはないでしょうか? これらをいったん見つめ直す時間がマインドフルネスの時間です。自動で動いている身体や思考を自分でコントロールできるようにしていきます。私の場合はまず「自分って何だろう?」というところから始まりました。脳?心臓?それともこの思考が自分?色々と悩みました。今は身体や思考と切り離されたもので、自分の身体を俯瞰するイメージでやっています。この辺りは人それぞれやり方があると思います。
「私は疲れている」ではなく「私の身体、特に脳が疲れを感じている」
「私は怒っている」ではなく「私の中に怒りという感情が湧いてきた、感情というのは一時的なものなのですぐに私の中から去っていくだろう」
というような考え方になる、というと伝わりやすいでしょうか。
人間の脳は、何も考えていないようで常に何かを考えています。それが脳の疲れ、さらには身体の怠さなどにつながっています。それに気付くことで、休憩する時のリラックスの度合いが大きく変わってきます。マインドフルネスのやり方には様々な方法があります。座って呼吸に注意を向ける「呼吸瞑想法」、ヨガのポーズをしながら行う「マインドフルネスヨガ」、身体の各部位に注意を向ける「ボディスキャン」などが代表的でしょうか。人によって合うやり方、合わないやり方があると思います。大事なのは、今の自分に注意を向けることで、「過去を思い出して辛くなっている自分」や、「未来を悲観したり予測したりしている自分」に気付いて、それをただ受け止めることです。それが、自分への理解や、集中力の増加などにつながっていると感じています。
気になる方はぜひ、マインドフルネスの本を手にとってみてください。おすすめは、マインドフルネスを医学の世界に取り入れた第一人者であるジョン・カバット・ジンの文献です。不思議とこういう人間になりたいなと思える本です。
なんとなく飲むコーヒーがとても美味しく感じたり、何気なく吹いた風がすごく心地よく感じたりする、そんな当たり前のようで素敵な体験こそが、何気ない幸せなのだと今では思えるようになりました。
ペンネーム:ぴーちょ
2020年9月24日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第100回『みなさんの不安な気持ちを和らげることができたら…』
-
みなさんこんにちは。BUC(バックアップセンター・きょうと)の「情報発信係」の編集長、Yです。いつもはこんな感じで情報発信係が前にグイグイ出てくることは無いのですが、今回は何と言っても記念すべき100回目です。編集長の特権で書かせていただくことになりました。
とは言うものの、私はここに通い始めてから数ヶ月。このブログの4年にわたる歴史を語ろうにも、当初のことは全く知りません。さすがにそれではマズかろうということで、過去の記事を読んでみました。
ブログの第1回目がアップされたのは2016年10月。タイトルは「秋のハイキング 嵐山の名所と自然を満喫!」でした。秋のハイキングか、いいなぁ。紅葉の季節だし、とても良い景色だったんだろうなぁ…。
BUCは京都駅前のビルの5階にあって、見晴らしはとても良いです。さらに交差点のはす向かいには東本願寺、その先には愛宕山などが見渡せて、休憩スペースのソファからそんな景色を眺めると、作業の疲れも少し和らぐような気がします。とは言え、いつもの部屋から外に出て、新鮮な空気を吸いながら、目の前に広がる美しい景色を味わうというのは、また格別の良さがありますね。想像しただけでリフレッシュできそうです。
私は休職中でも、いや休職中だからこそ、楽しみを見つけて心をリフレッシュすることがとても大事だと思っています。(休職して間もない頃は、「楽しむ」ということにどこか罪悪感を持ってしまっていましたが、こころを回復させるためにはやっぱり楽しみは必要ですよね。病気を治すにはその方が良いようです。)
今はコロナ対策の影響で開催できないものも多いのですが、それでもBUCではさまざまなイベント(OB交流会やファミリーミーティング、納涼会など)が催されていて、毎回とても楽しいです。出し物を練習したり盆踊りを踊ったり…といった機会も、大人になってからはなかなか無いので、実際にやってみると面白いものです。これも委員に選ばれたメンバーが企画を一生懸命練って準備してくれるおかげです。
私も委員をしたことがあるのですが、BUCで個人に与えられる課題(うつ病や認知療法、マインドフルネス等についての課題図書を要約する作業)と並行して各種イベントの準備をするので、マルチタスクが要求される実際の職場を疑似体験できて、復職の訓練にとても役に立ったなぁと思っています。
こちらのブログを掲載する目的も、イベントと同様、「メンバーの訓練の一環」という側面があります。書くことを通じて自身の振り返りも出来ますし、復職に向けての準備にもなります。しかしそれだけではなく、情報発信係としては「読んでいただく方の力になりたい」、とりわけ「BUCへの通所を検討されている方々や、通所して間もない方に向けて、不安な気持ちを少しでも和らげることができたら」という思いで続けております。私たちも休職中の身なので、しんどさや辛い気持ちは普通の人よりは理解できるつもりです。どこかで読んで下さっている方の気持ちがわずかでも「ふわっ」と軽くなるようなブログを目指して、これからもコツコツとやっていきたいと思います。
ペンネーム:編集長Y

2020年9月10日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第99回【BUCに通って良かったなと思うこと】
-
私はBUCに通い始めて約7ヶ月経ちます。
BUCに通って良かったことは沢山あります。はじめからそう思えていたわけではなく、通いだした頃は、「本の要約をしているだけで、復職できるのかな?私はここで何をやっているのだろう?」と焦りと不安でいっぱいでした。しかし、少しずついろんな講座に参加したり、他の通所者さんやスタッフさんと話したり、病気に関する本を読む中で、自分の気持ちが楽になってきていることに気づきました。今では、BUCに通って本当に良かったと思っています。
一番良かったことは、「同じ悩みや不安をもった仲間がいる」「相談や心配、アドバイスをくれるスタッフさんたちがいる」ということです。
仲間とは、年齢も性別も職種もさまざまですが、お互いの病気のことや休職から今までこと、BUCに通いだしてからの変化など、それぞれの話を聞けて共感し合える。「こんなこと話したら引かれるかな?」と思うこともなく、素直に話せる。それが一番大きかったです。
スタッフさんとは、初めはお互い探り探りでしたが、そのうち私の特性を掴んでいろいろアドバイスや励ましを頂きました。私はBUCに通所中、順調に回復していったわけではなく、何度も後戻りをしました。その都度、心配して声をかけてくれました。辛いときには、「早めに相談してくれたらよかったのよ」「頑張ったね」と優しく声をかけてくれ、一方、思考が歪んでいる時には、「それは根拠がないことでしょ」と指導を頂くこともありました。親のように親身になってくれる人がいる。後戻りして辛かったとき、自信をなくしてしまったとき、本当に救われました。感謝しています。
長くなりますが、もう一つ良かったことがあります。それは、「性格を変えるのではなく思考を変える」ということを学べたことです。「長所は短所、短所は長所」という諺のように、以前は、自分の短所を直すと長所も消えてしまい、私じゃなくなると悩んでいました。さらに、性格なんてそんな簡単に変えられないとも思っていました。けれど、性格ではなく思考を変えることによって、長所を伸ばし、短所を抑えることができると知り、講座にも前向きに取り組むようになりました。思考もすぐには変わりませんが、繰り返し練習することで以前よりは生きやすい思考になってきているのかなと感じています。
当初は、自分の感情に振り回されて気づかなかったこともありますが、こうして振り返るとBUCに通って良かったことは沢山あります。これからも、人生には辛いことやしんどいことが沢山あると思いますが、どんな経験も自分にとってプラスになると信じています。
ペンネーム:スイア
2020年8月27日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第98回「普通」になるまで続ける
-
BUCにいる時に「よく続けていらっしゃいますね」とスタッフの方に声を掛けられることがあります。それはデスクワークの時でもなく、講座の時でもありません。昼食の時です。
困ったもので、私は糖尿病も患っております。BUCに来る前に精神系の病院に入院していたのですが、ご存知のように病院食というのは少なくてお腹が減るので、こそっとおやつ的なものを食べておりました。ただ、私も気にしていなかった訳ではありません。「0 kcal」という、今思えば悪魔のささやきを発していたゼリーなどを食べており、大丈夫だろうとタカをくくっていました。
しかし、退院が見えてきた時に行った血液検査の数値が安田大サーカスのクロちゃんより悪い値でした。このため退院後はBUCへの通所と並行して糖尿病の改善にも取り組むことになりました。
主に行ったのは食事制限でした。特に炭水化物を減らすことが効果があると、いまさらながら分かったので、主食は豆腐にして米飯、麺は一切口にしないことにしました。食事を制限するというのは初めてで、かつBUCへの通所もあったので、とにかく大変でした。でも2〜3ヶ月するとそれほどでもなくなってきました。今は1年近く米飯と麺は食べていませんが、それで大丈夫ですし、数値も正常値を維持しています。
ここで冒頭の昼食時に戻ります。私の状況をご存知の方は「すごいね」と言ってくれます。それはそれで嬉しいのですが、私にとってはそういう食事はいつの間にか「普通」になっていたんです。
今回はしなければヤバいという危機感があったので、続けることが出来ていますが、効果が本当に出るかどうか分からないものを継続するというのは難しいことだと思います。ただ、それをすることによって少なくとも悪くはならないでしょうから、信じて続けてしんどい時期を乗り越えることが出来れば、そして今まであった懸念が晴れて、その状態が「普通」になることが出来たら、自分にとって糧になるのではないかと思います。簡単に言うと信じて続けられるかどうか、でしょうか。
今回の話、糖尿の話だったような気が・・・(笑)
(ペンネーム:T.S)
2020年8月13日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第97回「みんなちがってみんないい」
-
BUCに通い始めて半年が経ちました。様々なプログラムに参加し、休むことなく通えています。しかし、私の復職への道は最初から順調というわけではありませんでした。仲間であるメンバーにも一部の人にしか話していなかったのですが、実は私、BUCの通所は今回が初めてではありません。休職してすぐの2年ほど前にもBUCの門を叩いたことがあるのです。「家族に頼りたくない」という気持ちが強く、頑なに一人暮らしを続けていた私に主治医の先生が「定期的に通う場所がある方がいい」とすすめてくれたのがBUCでした。早く仕事に戻りたいという焦りもあり、ここに頑張って通えば仕事に戻れる!と、辛い心身にムチを打つようにして通っていましたが、今思えばかなり無理をしていたのだと思います。しんどすぎて、当時の記憶が殆どありません。約1か月しか通えず、結局実家に帰って療養生活を送ることになりました。
つらつらと過去について書きましたが、何が言いたいかというと、BUCに通い始めるタイミングは人それぞれ!ということです。回復には個人差があります。メンバーの中には、比較的しんどい段階から“とりあえず通う”ことで徐々に回復していく人もいるし、ある程度自宅等で療養してから通所してハイペースでステージアップしていく人もいます。一度目の失敗によりもうBUCには行きたくないと思っていた私も、一人で生活できるぐらいに回復してから始めた二度目の通所は、一度目とは全く違う感覚があり、同じことをするのでも、自分の病状によってずいぶん受け止め方が違うのだと実感しています。
ブログ読者の中には、様々な状況の人がいると思います。もし、休職中でしんどいけれど少しでもBUCに興味を持った人がいたら、ぜひBUCの存在を頭の片隅に置いておいてもらえたらと思います。きっとそれぞれ違う、自分に合ったタイミングがあると思うので。そんな風に思うほど、今はBUCに来て良かったなと思っています。(ペンネーム:ポッキー)