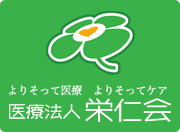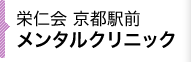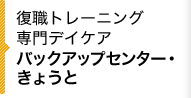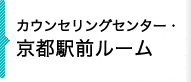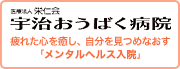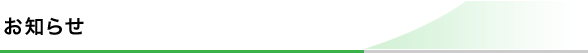京都市 下京区 心療内科 精神科 メンタルクリニック カウンセリング 復職トレーニング専門デイケア
- ホーム >
- お知らせ
BUCきょうとのブログ
2020年7月30日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第96回「マインドフルネスとの出会い」
-
社会人になってから、メンタルヘルスに興味があり、それを健康な状態に保つことは必要なことだと感じていました。いくつか目に留まった本を数冊読んだことはあったのですが、どれもピンとくることはなく自分に合う良い本に出合えませんでした。
しかし、こちらに通い始めてから様々な課題図書を読み進めていくなかで「最高の休息法」という本に出会い衝撃を受けました。
何に衝撃を受けたのかと言うと、
一つ目は、運動して疲れる身体と一緒で脳も疲労し休息が必要だということ。
二つ目が、脳疲労の最大要因の1つが「雑念」であるということでした。
「脳に休息は必要ないし、必要だとしてもどう休ませていいか分からない。」
これがこの本に出合う前に私が思っていたことでした。
例えば、身体の疲労ですと運動をすることで疲れを感じることが出来ますが、脳の疲れは気付きにくく、人によって疲労の出方は違います。
そういった状態のなかで出会ったのが、この本で紹介している「マインドフルネス」という瞑想を使った休息法です。
マインドフルネスとは、今現在起こっている事に注意を向ける心理的な過程であり、瞑想およびその他の訓練を通じて発達させる技法です。
瞑想の一種ということをイメージして頂ければ、何となくどんなものかイメージしやすいかもしれません。
語義としては、「今、この瞬間の体験に意図的に意識を向け、評価をせずに、とらわれのない状態で、ただ観ること。」
なんだかとても難しそうだし、どういうことかよく分からない説明です。
でも本によると、Google社などのアメリカ大企業の研修に取り入れられているぐらいだし効果があるのでは?と期待を込めて始めてみました。
実際にやってみると、本に書いてあった通り「頭がスッキリする」感覚を得られることが出来ました。最初はやり方の感覚をつかむのが難しくうまくいかなかったですが、継続していくことで、だんだんと感覚をつかむことが出来ました。
具体的なやり方は上記の本を読んで頂くかYouTubeで「マインドフルネス」と検索すると動画が出てくるので是非試してみてください。
マインドフルネスは、スポーツと同じで練習しないと身につかないですし、継続していかないと上手くならないものなので、是非この機会に習慣化していこうと取り組んでいるところです。
2020年7月16日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第95回「私流、夏バテ防止対策」
-
毎日暑い日が続きますね。じめじめして本当に不快です。さて皆さん、普段の入浴はどうされていますか?暑いし、浴後に汗が止まらないし、ってことでシャワーだけで済まされていませんか?
暑い夏こそ、週に1回くらいは湯船につかりましょう。どうしても空調の効いた屋内にいると汗腺(汗をかくところ)が鈍り、発汗による体温調整機能が低下してしまいます。そうすると汗を適切にかいての体温コントロールが上手くいかず、熱中症の症状を引き起こしやすくなります。運動しないことで筋肉が衰えて、ちょっと動いただけでバテてしまうのに似ていますね。
しっかり湯船につかって汗をかき、「今は暑い夏だ、しっかり汗をかけ」と体に思い出させてやりましょう。汗をしっかりかくことで、汗と共に老廃物が出て美肌効果も期待できます。もちろん、入浴前後の水分調整はお忘れなく!
(ペンネーム:Y.T)
2020年7月 2日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第94回「ギターでつまずき、BUCでお世話になった話」
-
僕の通所のきっかけは「ギター」です。冗談だと思うでしょう?でも本当です。
去年の夏頃にうつ状態になり、休職が始まりました。そして症状が一旦落ち着いた頃、主治医の先生から「何か全く新しい趣味を」とアドバイスがあり、特に深く考えずギター教室に通い始めました。
現在45歳。まあまあのおじさんで、物覚えもあまり良くありませんが、それでもギターは少しずつ上達しました。数ヵ月が経って、精神状態も上向いて来た頃、復職についても「何とかなるのではないか?」と思えるようになって来ました。しかしあることがきっかけで、そんな気持ちは吹き飛んでしまったのです。
ある日、ギターの先生から簡単なアドリブ演奏を求められました。「はいっどうぞ」。そう言われた瞬間、メトロノームは容赦なく時間を刻み始め、僕は準備していたことが頭から飛んで、もう何をしてもムダなような気がして。情けないくらい完全に固まりました。ちょうどそれは、久しく忘れていた仕事の現場の感覚そのものだったのです。「復職が怖い。」本気でそう思いました。
しかしそんな中、僕にとって幸運だったのは、通っている病院の隣にBUCがあったことです。相談してすぐに主治医の先生からBUCを紹介して頂きました。
家族、上司、同僚。周りに人はいるけれど、深い話をするのは案外難しいもので。休職が長引けば長引くほど、どんどん周りの世界から取り残されて行くように感じることもありました。でもBUCなら、スタッフさんだけでなく、通所しているメンバーの方々にも正直な自分の気持ちを打ち明けられるのが心底ありがたいと感じています。
この文章を読んで下さっている方の中には、通い始めて日が浅い方もいらっしゃるかと思いますが、一度思い切って周りに話しかけてみて下さい。きっと新しい世界が開けると思います。ここには自分を飾らなくても受け入れてくれる仲間がいます。みんなを信じて、支え合って、一緒に前へ進んでいきましょう。
ペンネーム:M.Y
2020年6月18日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第93回「海賊王になる」
-
「海賊王に、俺はなる!!!」
『ワンピース』のルフィは、言います。
自分の気持ちの赴くまま、その強い想いに賛同する仲間たちと、いつか夢を実現するため、数々の困難に立ち向かい、乗り越え旅をしていきます。
ルフィにとっての「海賊王」は、財宝でも地位でもなく、この海で一番自由だということ。
ワンピースを探す旅においての仲間との出会い、絆、それぞれの夢を叶える過程により、ルフィは「海賊王」になっていくんだと思います。
ルフィは「船長」ですが、悪魔の実を食べてしまったので泳げません。剣も使えません。航海術も料理もできません。自分には仲間の助けが必要なことを自覚していて、そのため仲間を全力で守ります。
長い旅の途中で、ルフィは兄エースを失います。
大切なものを失い、自分の弱さを思い知らされ、自暴自棄になっていたルフィに元王家七武海のジンベエが問います。
「失った物ばかり数えるな!!! 無いものは無い!!!
確認せい!!!おまえにまだ 残っておるものは何じゃ!!!」
そして、兄を亡くした今も、かけがえのないものが自分に残っていることに気づきます。
「仲間がいるよ!!!あいつらに会いてぇよォオ!!!」とルフィが叫びます。
ルフィの強さ。それは、自分の弱さを知っていること。
そして、自分をさらけ出せ、すべてを受け入れてくれる仲間がいることです。
私は、ずっと自分は強くないといけないと思っていました。
部下を守るために、理想の上司でいなければと思い込んでいたのです。
理想の上司なんて人それぞれ、言葉を変えれば「自分にとって都合のいい上司」です。
私は、実体のないものに捉われ、自分を見失っていました。
自分は弱い。でも弱さを知っているからこそ、誰より人の気持ちがわかって、助けることができる。
本当の強さは、自分の弱さを受け入れ、それを活かすこと。
そして、自分に正直でいること。
『ワンピース』は、私にとって必要なことを教えてくれるバイブルです。
私には、「海賊王になる!」なんて大きなことは言えませんが、
一緒に乗り越えてきた仲間がいます。
もう二度と会えない仲間もいます。
その想いを繋いで、いつかまた仲間たちと一緒に過ごせる日を目指します。
その時は、「宴」ですね。
歌って踊ってベロンベロンに酔っぱらって、全部笑い飛ばします。
いつか、その日が来ることを願って。
ペンネーム: 一休
2020年6月 4日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第92回【不安と上手くお付き合いする方法】
-
皆様、お初にお目にかかりますジュン満願郎と申します。突然ですが皆様、今何か不安はお持ちでしょうか?現在のご時世に鑑みると、誰もが不安を持っていて当たり前のような気がします。不安を感じるというのは、何となくマイナスなイメージがあります。それは、恐らく不安という感情が、身や心に迫ろうとする脅威を感じ取った際に出る、反射的警告であるからだと考えます。何かに自分が脅かされそうに感じるのは、少なくとも気持ちの良いものではありません。一方で、不安を全く感じ取れない場合、それらの脅威に対処することができなくなるため、やはり無くてはならぬものであるとも考えます。
少し話が逸れてしまいますが、私がこちらにお世話になっているきっかけは、うつ病を発症したためです。私にとってこの病の最も恐ろしい所は、「今まで当たり前のようにできていたことが出来なくなる病である」という一言に尽きます。その中でも、「不安を解消できず、漠然と延々悩みすぎること」は、中々に辛いものでした。四六時中、その事柄の悪いイメージがぐるぐると引っ切り無しに思い浮かび、抜け出せなくなるのです。
では、どうしたらそんな不安と上手く付きあうことができるのでしょうか?
これは、あくまで私の場合ですが、それは不安を含めた感情への理解にありました。そもそも、不安は何によって、もたらされるのでしょうか?自分以外の人や自然、自分が関わりを持つものから直接的には関係のないものまで、様々考えられると思います。しかしながら、どんなものであってもそれを不安に思うのは自分であり、その不安という感情は他人のものではありません。不安以外もそうですが、自分自身の感情とは、自分だけのものであり、それを想起するのは自分以外の何者でもないのです。これは、考えると当たり前のことなのですが、私にとっては天啓のようなものでした。つまり、不安から自分を苦しめているのは、他ならぬ自分であったのです。これに気づくと、自分が自分の首を絞めて、勝手に唸っているというかなり滑稽な映像が思い浮かび、随分と気が楽になりました。
不安を感じることは良い悪いではなく、必要な事だと思います。しかし、不安とばかりデートしては、身も心も持ちません。時には、こっぴどく断っても良いのです。何故なら、不安とは離れられない仲であり、ずっと付き合わなければならない伴侶の1人であるとも考えられるからです。
(ペンネーム:ジュン満願郎)
2020年5月22日 (金)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第91回【休日にやっている気分転換】
-
私が休日にやっている気分転換の方法を紹介します。
私は大津市に住んでおり、いつも身近に琵琶湖があります。この自然資源を活用して、「ウォーキング」と「ワンコイン電車旅」をしています。
ウォーキングは、大津港から膳所城址公園までの間、湖岸沿いに整備された遊歩道を歩きます。京都から見るのとは違った形の比叡山が見えます。空気が澄んだ日には、遠く湖の向こうに伊吹山や鈴鹿山脈を望むことができます。秋には街路樹が赤や黄色に色づき、とてもきれいです。自転車で湖岸沿いを走るのも気持ちが良いものです。
ワンコイン電車旅は、大津駅から隣の山科駅まで、琵琶湖線・北陸線・湖西線経由で琵琶湖を一周する約3時間の旅です。運賃は1駅分の190円です(駅員さんに確認しました)。車窓からの風景を眺めても、本を読んでも良いし、電車の揺れに任せて眠るのも心地良いです。雨の日もまた趣があります。



ペンネーム:SS
2020年5月 7日 (木)
- 【BUCきょうとメンバーブログ】第90回:【「調子が悪い」と言える勇気】
-
私は通所を始めて半年以上経過しているのですが、まだ安定しているとは言い難い状態です。回復傾向とは言え、好不調の波が大きくBUCを連続で休むこともあります。ですので、なかなかステージが進まず、自分で悶々とすることもしばしばです。
1週間で4日休んでしまった時のことです。もちろんスタッフの方が心配して声を掛けてくれました。その時、自己嫌悪で、とにかくいろいろ言われたくなくて、半ば八つ当たり的に「休んでしまって、一番へこんでいるのは私です。」と話しました。ただ、自分の調子が悪いことを正直に伝えられて、受け入れてもらったことで少し気が楽になりました。
ここに来る以前は入院をしていたこともあります。入院では「クリティカルパス」と呼ばれる、入院期間に対して生活リズムを整える期間や薬の調整をする期間の目安があり、通常の症状の場合は、この期間を基本として治療を受けます。ですが、私は薬の調整の目安が過ぎても症状が改善した感じがしませんでした。担当のドクターから「どうですか?」と聞かれた時、私は残り期間のことを考えましたが、このままの状態では回復していく自分の姿が想像できず、「調子が上がりません」と正直に答えました。その後、薬の調整を続けたことで効果が出て、自分が納得できる退院ができました。あの場面で調子が悪いと言わなかったら、ずっと低空飛行のまま復帰していたと思います。まあ結局、今はこちらにお世話になっている訳ですが・・・。
BUCでも入院でも、本当は何かしっくりしない症状を感じていても、遠慮や体面を考えて「大丈夫です」と言ってしまうことがあるかも知れません。しかし、自分の調子が上がらないことに対して勇気を持って打ち明ければ、自分がそこであきらめてしまわない限り、ドクターやスタッフもあきらめません。
もし、ご本人から「調子が悪い」というような言葉を聞かれた時は、それは自分の状態が分かっているサインであると同時に、勇気を持って伝えることができていると感じて下さい。それは回復への一歩を進んでいるのだとあきらめず接して頂ければ、復職への道も見えてくるのではないかと思います。(ペンネーム:T.S)
2020年4月23日 (木)
- BUCきょうとメンバーブログ】第89回:【長年のモヤモヤと、幸せな結末】
-
「子供の頃に聴いた曲が何だったのか思い出せず、モヤモヤする」っていうこと、ありますか?僕はよくあります。そんな中、先日Youtubeでその内の1曲が偶然見つかり、長年のモヤモヤが解決してスッキリするという経験をしました。Youtubeって偉大ですね。
ちなみにそれは「レンズマン」という80年代のアニメのエンディング曲でした。原作は戦前のアメリカのSF小説で、レトロフューチャー感がいい味を出しています。久しぶりにその曲を聴いてみると、「すごいメカが満載の宇宙船」とか「異星人の仲間」とか、そういうポジティブでキラキラした未来に憧れた少年時代の記憶が蘇って来ました。と同時に、ふと「今の作品にないもの」も見えたような気がしたのです。
昨年末に観たスター・ウォーズの最終章。映画館でエンドロールが流れた時、「お金もかかってて見せ場も盛りだくさんだったけど、子どもの頃に観たスター・ウォーズに比べて、ほんの少し何かが足りないんだよなぁ…」という感覚が残りました。でもそれが一体何なのか、正直あんまりよく分からないままモヤモヤしていたのです。そんな折、Youtubeの一件をきっかけに、そのモヤモヤの正体が自分の中にある「未知の世界へのワクワク感」みたいなものだと気付きました。
「ああ、なるほど。」一応の正体らしきものを自覚し、とりあえずはスッキリした僕。しかし人間とは欲が深い生き物です。そんなきわめて個人的な感覚を、「誰かと分かち合いたい」。そんな風に考えるようになりました。そこで、本が好きな大学時代の先輩たちと連絡を取って、理解してもらえるかどうか不安に思いながら、そのフワフワした感覚を(それ以上にフワフワな言葉で)恐るおそる説明してみたのです。すると、先輩のうちの一人が、「ああ、それは『センス・オブ・ワンダー』と呼ばれるものだよ」と(わりと秒で)教えてくれました。
「センス・オブ・ワンダー」。ネットの辞書によると「一定の対象(SF作品・自然等)に触れることで受ける、ある種の不思議な感動、または不思議な心理的感覚を表現する概念であり、それを言い表すための言葉」とありました。さらに「それは1930~40年代のSF作品に見られる特徴であり、70年代におけるアメリカのSFはそれを取り戻そうとした傾向が見られる」とのことでした。それを読んだ時、僕はなんとも言えない嬉しさがこみ上げてきたのでした。
この掴みどころのない感覚を他の人に話して理解してもらえたこと、この感覚が予想よりもメジャーなものだということ、しかもそれをひと言で表す言葉まで存在するということ。「言葉って不自由だけれど、それでもチャレンジして人と話して良かった。同じ感覚を他人と分かち合うって素晴らしいなぁ。」そんな感覚を久々に味わえて、幸せな瞬間でした。
(ペンネーム:M・Y)
2020年4月 9日 (木)
- BUCきょうとメンバーブログ】第88回:「自分で選ぶことは大切」
-
兄弟の家庭に、育児本を読みあさって、悩みに悩んで数冊お祝いにと送ったことがありました。お礼の返事ももらい、お勧めの本があればまた送って欲しいと言われ追加で送ったりもしました。一般的にも自己評価的にもいい本だったので、正しいこと、ためになることはたくさん書かれていたと思うのですが、奥さんから一部「母親としての役割の自分のいたらなさ」を責めるような返事を貰い、ショックだったのを覚えています。奥さんは、本に書いてある母親像と自分とを真っ向から比較されていて、「~ねばならない」に囚われていて、とても申し訳ないことをしたなと思いました。
前置きが長くなりましたが、同じようにBUCでも、課題図書を読んでいたり、講座を受けていたり、メンバーやスタッフとのやり取りの中で、いいことをたくさん学んで話して考えていると思います。ですが、そこから得たことの全部や多くを守ろうとすると、「~ねばならない」にしばられて、しんどくなってしまうのだなと兄弟の奥さんのことから気をつけようと思いました。色々な人と話したり、情報媒体から知識を得ることはいいことだと思うのですが、その後の自分に合った型に調整(咀嚼)して、自分にとって合ったものなのかを最後は自分で取捨選択して、多くを持ちすぎないようにする行程が大切なのかなと個人的に思いました。調整と取捨選択は、得たことをそのまま鵜呑みにして思考停止にならないように、自分で考えて、自分に責任をもつための大切な行程であると思います。持つ荷物を重くしすぎて、自分を潰してしまわないようにしていきたいです。何ごともほどほどに。
(ペンネーム:MK6)
2020年3月26日 (木)
- BUCきょうとメンバーブログ】第87回:「春までにしたいこと」
-
私の「春までにしたいこと」は鉄棒の逆上がりです。
これを見ると、「何それ?」と思われるかもしれませんが、今年1月上旬に6歳(保育園の年長組)の息子が「パパ、ぼく、逆上がりができひんねん。」と言うので、「よっしゃ!パパが見本みしたる!」と意気込んで鉄棒に向かったものの、逆上がりどころか足すら全然上がらなくて、余計に子どもを落ち込ませる羽目になってしまったことがきっかけです。